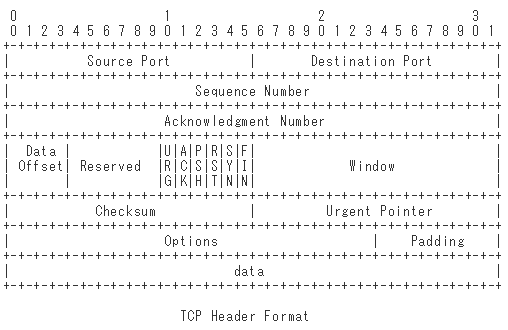作成:2018年11月30日
製造物責任法(以下、PL法)とは、製造物の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合に、被害者は製造会社等に対して損害賠償を求めることができる法律です。技術士第一次試験の適性科目で毎年のように出題されていますし、基礎科目(設計・計画)でも簡単な穴埋め問題が過去何度か出題されています。
PL法の要点を押さえることで、適性科目と基礎科目の両方の得点アップが見込めますね。
PL法でいう「欠陥」とは?
製造物が有している特性や通常予見される使用形態、製造物を引き渡した時期等を考慮した場合、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること欠陥といいます。
欠陥であるかどうかは、上記のとおり「時期」も考慮の対象となります。したがって、製造業者が引き渡した時期における科学または技術に関する知見によって、当該製造物に欠陥があることが認識できなかった場合、欠陥とはなりません。
PL法に基づく損害賠償を受けるには?
被害者が、「製造物に欠陥が存在していたこと」「損害が発生したこと」「損害が製造物の欠陥により生じたこと」の3つを明らかにすることが原則であり、製造業者や販売業者等の故意または過失を立証する必要はありません。
つまり、製造業者等は、製造物の欠陥によって損害を与えた場合、過失の有無にかかわらず賠償する責任がある、ということですね。
なお、PL法に基づき損害賠償を請求できる期間には制限(時効)があります。
具体的には、被害者が損害及び賠償義務者を知った時から3年、または製造物を引き渡したときから10年を過ぎると時効となります。
PL法における「製造物」とは?
「製造または加工された動産」を製造物と定義されています。
なので、不動産は製造物ではありません。
PL法における「製造業者等」とは?
「製造物を業として製造、加工した者」は当然対象となりますが、「製造物を輸入した者」も製造業者等に含まれることに注意が必要です。
また、いわゆるOEM製品の販売者も対象となり得ます。
以上、PL法について整理してみました。
上記内容を押さえておけば、一次試験は大丈夫だと思います。